【書評】「西洋の敗北と日本の選択」・エマニュエル・トッド著・文集新書
福井 杉本達也
ベストセラー『西洋の敗北』の著者:エマニュエル・トッドの最新作である。中身はこれまでのここ1~2年の『文藝春秋』に掲載した論文を1冊の新書にしたといってよい。文章の骨子は既に『文藝春秋』で読んでいるはずであるが、やはり月刊誌ということもあり、読んだ当座から、右から左にどんどん忘れ去ってしまうことが多い。それを1冊にまとめ直すと、新たな視点も生まれてくる。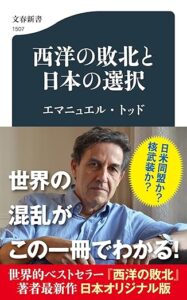
1 「民主主義」という言葉を「労働」から考える
著者は「米国、英国、フランスなどでは、グローバリゼーションによる生産基盤の海外移転が進みすぎて、もはや後戻りができなくなっている」と産業空洞化の悪影響を指摘する。「労働」は「単に『お金を稼ぐ』ためではなく、『自己実現をする』ためでもある」が、「米国の労働者階級は、安価で質の良い製品を自分で『生産』せず『消費』」してきたため、「『生産者』と違って『消費者』は『共同体』には属さない存在」だとする。続けて、「『民主主義』は『消費者』ではなく、『労働者』によって支えられるもので、そうした『労働者』が消滅したことで米国の『自由民主主義』は『リベラル寡頭制』へと変質」したとする。「労働」という観点からは、「産業基盤が残っている日独の方に『民主主義』に担い手が残っている」はずだが、残念ながら日本とドイツは「米国の〝占領〟が続き…『主権』を欠いていて」民主主義国家とはいえないとする。
同じ米国の占領下にあっても、韓国の李大統領は9月21日のSNSで、「重要なことはこうした軍事力、国防力、国力を持っていても、外国の軍隊がなければ自主国防が不可能だと考える一部の屈従的思考だ」と指摘し、「国防費をこれほど多く使う国で、外国軍隊がなければ国防ができないという認識を叱責した盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領が思い浮かぶ」と言及した。だいぶ日本の与野党の指導者とは心構えが違うようである。
2 「トランプ関税」をどうみるか
著者は「基本的に保護主義に賛成です」とし、「自国の産業を守るには、ある程度の保護主義が必要なのです」としつつも、「保護主義政策が効果を持つには、輸入品に関税を課すだけでは不十分であることです。『優秀での能力があり勤勉な労働人口』が必要なのです」と指摘する。それを念頭に、著者の診断は「米国はすでに手遅」だと引導を渡している。「米国のエンジニア不足」、「技術者や質の高い労働者も不足しています」「トランプの高関税から実際に『利益』を引き出すには優秀な労働力が必要なのに、今日の米国はこうした労働力を欠いている」「トランプの高関税は、実際には供給の困難、生活水準の低下、インフレの悪化」を引き起こし、「失敗するだろう」と切り捨てた。
さらに続けて著者は「『経済を守れ!』『産業を守れ!』『国内でモノをつくれ!』と繰り返すトランプは、ある意味、優れた直感の持ち主ですが、『保護主義の理論』きちんと理解できていない」と一旦上げてから、こき下ろす。「トランプがBRICSを脅迫して『ドル覇権』を死守しようとした時に、そのことが露わになりました」「むしろ米国の国内産業の復活を妨げているのは、この『覇権通貨ドル』なのです」「『ドル覇権』が『抽象的な記号でしかない通貨記号(=ドル)』と『外国からのモノ』との交換を可能にしているのです」「だから米国では、高学歴者ほど、産業やモノづくりの就職につながる科学やエンジニアの分野ではなく、抽象的な通貨記号であるドルという富の源泉に近づくために、金融や法律の分野に進んでいます」と分析し、「ひたすらドルという抽象的な貨幣にこだわる姿勢、ドル覇権を何としてでも維持するという意思は、トランプ個人の失敗だけでなく米国自体の失敗でもあります。」とし、「彼の大統領としての役割は、ロシア、さらにはイランや中国に対する軍事上の敗北、産業上の敗北を、要するに『世界における米国覇権の崩壊』をいかにマネジメントするかにあります」と言い切っている。
3 自己目的化した暴力の行使―イスラエル
著者はイスラエルについて「暴力自体が自己目的化している」とし、イスラエルの行動は「ニヒリズム」であるとする。イスラエル国家の振る舞いは「社会的・宗教的価値観を失い(『ユダヤ教・ゼロ』)、国家存続のための戦略に失敗し、周囲のアラブ人やイラン人に対する暴力の行使に自己の存在理由を見いだしている国家」であると定義する。
有名な『戦争論』を書いたクラウゼビッツによれば「戦争は決して政治的関係から切り離しえないものである。もし切り離して考えるようなら、関係するあらゆる糸が切断され、戦争は意味も目的もないものとならざるをえない。」とし、「戦争で何を達成するかが戦争の目的であり、戦争で何を得るかが戦争の目標である。この基本的構想により、すべて方向性が決まり、手段の範囲、力の分量が決められる」としているが、著者は「イスラエルは本来のアイデンティティを見失っている」「敵対勢力の指導者や幹部といった個人をターゲットにした暗殺には、戦略的意味はなく、自己目的化した『殺人要求』」を感じるとする。「イスラエル人の無意識の深層では、今日、『イスラエル人であること』は、もはや『ユダヤ人であること』を意味せず、『アラブ人やイラン人と戦うこと』を意味」するとする。つまり、「暴力的」こそイスラエルの目的であって、そこに「合理的」目的を定義することはできないということである。
10月8日、トランプ米大統領は、イスラエルとイスラム組織ハマスがパレスチナ自治区ガザを巡る和平計画の「第1段階」で、全ての人質を「間もなく」解放し、イスラエル軍がガザの一部から撤収すると発表したが(福井:2025.10.10)、スコット・リッター氏は10月9日のYouTubeで、これはハマスの勝利であるとの見解を示した。戦争を続けることを自己目的化していたイスラエルが停戦を受け入れざるを得ないこと自体がイスラエルの敗北であるということである。トランプの調停は、停戦だけが実行され、後の20項目については何も実行されることはないであろうと述べている。ハマスの武装解除もないであろう。

参考になりました。
私は、昨年購入の「西洋の敗北」を、少しずつ噛みしめながら、やっと本日
終章「米国が『ウクライナの罠』にいかに嵌ったか1990-2022年」を読み終えました。
歴史への洞察力、深い見識に感服しております。
混迷の欧州/世界に一条の光明を見出した思いです。