<<冷戦思考・関税圧力に反対する「天津宣言」>>
2001年に設立された上海協力機構(SCO)の首脳会議が、20カ国以上の首脳に加え、国際機関の代表者も参加し、8月31日から9月1日まで中国の天津で開催された。
加盟国は、インド、イラン、カザフスタン、中国、キルギスタン、ロシア、タジキスタン、パキスタン、ウズベキスタンであり、2024年7月4日、ベラルーシが正式に加盟、オブザーバー国として、アフガニスタンとモンゴル、対話パートナー国に、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、エジプト、カンボジア、カタール、クウェート、モルディブ、ミャンマー、ネパール、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、トルコ、スリランカが参加している。
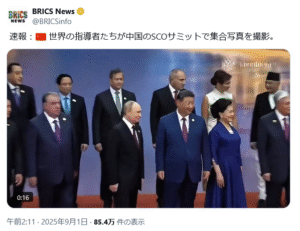 これら諸国の首脳が出席する、SCO史上最大規模の首脳会議となったわけであるが、そのような事態を強力に推し進めたのは、当事国の努力はもちろんであるが、トランプ米大統領の全世界に対する無法かつ不当な関税戦争であったことは間違いない。
これら諸国の首脳が出席する、SCO史上最大規模の首脳会議となったわけであるが、そのような事態を強力に推し進めたのは、当事国の努力はもちろんであるが、トランプ米大統領の全世界に対する無法かつ不当な関税戦争であったことは間違いない。
SCO首脳会議が採択した「天津宣言」は、「国際システムがより公正で平等な多極化の方向へ進化している」一方で、「地政学的対立は激化の一途をたどっている」と指摘し、「加盟国は一方的な経済制限措置に反対する」ことを明確に確認し、さらに、「冷戦思考」として「他国の内政干渉への反対」、「イスラエルとアメリカがイランを攻撃したことに対する強い非難」の文言まで盛り込まれている。
その「他国の内政干渉」への象徴が、「インドは石油や軍事製品のほとんどをロシアから購入」している、「ウクライナ戦争を煽っている」として、トランプ政権が対インド、50%関税という途方もない「一方的経済制限措置」を強行したことであった。トランプ大統領は、インドは米国の脅しに屈し、ロシアからの原油購入停止に同意する以外に選択肢がないと考えたのだろう。
ところが、事態はトランプ氏の思い通りにはいかず、対中国戦争でインドを同盟国の位置付けまでしていたはずが、トランプ氏にとってはむしろ最悪の事態に自らを追い込んでしまったのである。
今回、7年ぶりに訪中したモディ首相は、インドがロシアからの原油購入をやめるつもりはないことを示唆すると同時に、「相互信頼、尊重、そして感受性」に基づき、中国との関係を前進させていくというインドの明確な決断を表明し、中国の習主席は「世界は変革に向かっています。中国とインドは、最も文明的な二国です。私たちは世界で最も人口の多い二国であり、グローバル・サウスの一部です。…友人であり、良き隣人であり、龍と象が共に歩むことが不可欠です…」と応じ、モディ首相と習近平主席は、両国は「開発パートナーでありライバルではない。相違点を紛争に発展させるべきではない」と宣言し、強調する、中国・インドの関係改善・協力強化をもたらしたのであった。
ニューヨーク・タイムズ紙は、「中国東部で、ほぼ間違いなく世界の反対側の聴衆に向けた光景が見られた。西側諸国と連携しない三大国、中国、ロシア、インドの首脳が、月曜日のサミットでまるで親友のように笑顔で挨拶を交わした」、「インドのナレンドラ・モディ首相とロシアのウラジーミル・V・プーチン大統領が手をつなぎ、世界の首脳で埋め尽くされた会議場へと歩みを進める。二人はまっすぐ中国の習近平国家主席のもとへ向かい、握手を交わし、円陣を組む。通訳が加わる前に数言交わす。プーチン大統領は満面の笑みを浮かべ、モディ首相も大きな笑い声をあげる。ある場面で、モディ首相は両首脳と握手を交わす。」、タイムズ紙はさらに、SCO首脳会議は「中国とロシアに、イラン、カザフスタン、キルギスタン、ベラルーシ、パキスタンといったパートナー国を結集する場を与えた」と報じている。
 9/1、こうしたモディ首相と習近平主席、プーチン大統領の和気あいあいたる会談に反発して、トランプ大統領は米印貿易を「一方的な大惨事」と非難し、怒りをぶちまける声明を自身のメディア・Truth Socialに投稿している。
9/1、こうしたモディ首相と習近平主席、プーチン大統領の和気あいあいたる会談に反発して、トランプ大統領は米印貿易を「一方的な大惨事」と非難し、怒りをぶちまける声明を自身のメディア・Truth Socialに投稿している。
「あまり知られていないことですが、インドとは米国との取引はごくわずかですが、インドは米国と莫大な取引を行っています。言い換えれば、インドは最大の「顧客」である米国に大量の商品を売ってくれますが、私たちもインドにほとんど商品を売っていません。…完全に一方的な大惨事でした!また、インドは石油や軍事製品のほとんどをロシアから購入しており、米国からはほとんど購入していません。インドは現在、関税をゼロに引き下げると提案していますが、手遅れです。何年も前にそうすべきでした。これは、皆さんに深く考えていただくための単純な事実です。」
「手遅れ」なのは、トランプ氏自身であろう。
<<「傍観者、もしくは敵対者」>>
今回のSCOサミットのキーポイントとしては、
* SCO加盟国を結束させる原則として、内政不干渉、主権尊重、武力行使または武力による威嚇の拒否、そして一方的な制裁を強制手段としての反対を明確に確認した。
* 天津宣言の中で、これら「一方的な強制措置」が、「国際法を損ない」、世界貿易機関(WTO)および国連憲章の規範に反する、ことを明確にした。
* SCOは、国連憲章に正当性を確固たるものにすることで、米欧・西側諸国の一方的な「ルールに基づく」枠組みが、その原則に反するものであるものと位置付けてた。
* SCO は世界人口の 41%、世界 GDP (購買力平価) の 34%、世界陸地面積の 24% を占め、さらに拡大することが確実になっている。
* そしてSCOは、西側諸国の支援や拒否権を必要としない並行システムとして既に機能し、拡大、発展している現実を世界に示した。
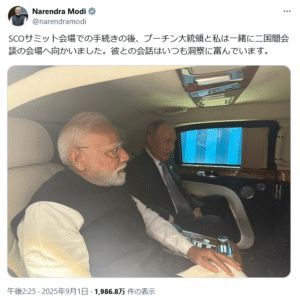 SCOサミットは、さらに、以下の重要な具体的成果と展望、国際的課題の解決への取り組みを明らかにしている。
SCOサミットは、さらに、以下の重要な具体的成果と展望、国際的課題の解決への取り組みを明らかにしている。
* 上海協力機構の銀行からBRICSへの融資、そしてASEANとGCC間の潜在的な協調まで、西側諸国の監視なしに行動できる手続き上の道筋が確立された。
* SCOが、BRICSを補完する機関として多極化プロセスをより一層加速させる軌道を確固たるものにした。
* 新開発銀行の設立と自国通貨建て貿易の推進により、BRICSは現在、西側G7に対抗できる世界貿易発展の重要な役割を担う段階に至っている。共同投資やインフラプロジェクトへの資金提供にとどまらず、加盟国が西側諸国の金融メカニズムへの依存を減らし、制裁の影響を緩和する上でも大いなる前進である。
* アジアの貿易と基準を形成する10カ国からなる東南アジア諸国連合(ASEAN)は、SCOおよびBRICSのプロジェクトとの連携を強めている。
* バーレーン、エジプト、カタール、クウェート、サウジアラビア、UAEは既にSCOの対話パートナーであり、湾岸協力会議(GCC)とこれら6つのアラブ諸国は、より広範な石油輸出国機構(OPEC+)を通じて政策を調整し、主要な原油供給のコントロールを可能にしている。
* サミットではまた、人工知能(AI)による安全保障上の脅威の防止、軍事協力の深化、核兵器不拡散条約(NPT)の厳格な履行の維持に向けて協力する共通の意思も強調された。彼らは、すべての国がインターネットを規制し、自国のデジタル空間を管理する主権的権利を有することを再確認した。
* SCOは、麻薬密売対策における協力強化への支持を表明し、宇宙空間を武器のない領域として維持することを提唱した。また、国連安全保障理事会によるイランへの制裁を復活させる「欧州3カ国」の取り組みには、そのような行為は違法であるとして反対を表明した。
* SCOは、中央アジア中核諸国だけでなく、ベラルーシ、イラン、パキスタンの大統領も出席し、マレーシア、アルメニア、アゼルバイジャンは正式加盟への関心を示した。こうした参加者の多様性は、SCOがユーラシアを越えて、政治体制と開発モデルの多様性に根ざした、新たなグローバリゼーションの中核へと進化していることを示している。
このような事態の進展は、「自国ファースト」「自国第一」路線ではなく、多国間協力・協調、世界の緊張緩和と平和への前進にとって不可欠なものであろう。問題点や矛盾点が広範に存在しているとはいえ、それらを克服する粘り強い、絶え間ない努力こそが要請されている。
ところが、この前進への過程に、米国はもちろん、日本を含むG7、欧州連合(EU)は、「傍観者、もしくは敵対者」でしかない、まさに米欧覇権の終焉、そのような現状こそが、国際的な政治的・経済的危機を深化させているのである。
(生駒 敬)
