【書評】「戦後史の正体」
孫崎亨著 (創元社 2012-08-20 1500円+税)
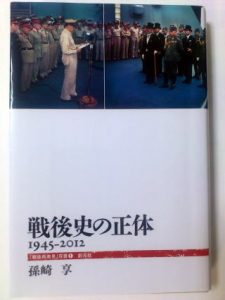 9月中旬だったか、NHKが吉田茂を題材にしたドラマを放送していた。いわく、占領国アメリカに抵抗して、国民を守った首相吉田茂を描いたのだそうだ。しかし、本書によると、占領軍GHQとマッカーサーの指示は、何でも無条件に受け入れた「ポチ」首相吉田茂だった、というのが真相のようだ。
9月中旬だったか、NHKが吉田茂を題材にしたドラマを放送していた。いわく、占領国アメリカに抵抗して、国民を守った首相吉田茂を描いたのだそうだ。しかし、本書によると、占領軍GHQとマッカーサーの指示は、何でも無条件に受け入れた「ポチ」首相吉田茂だった、というのが真相のようだ。
本書は、戦後の政治史を、日米関係への態度を軸に読み解いたものです。
「・・本書は、これまで語られることのなかった「米国からの圧力」を軸に、日本の戦後史を読み解いたものだからです。こういう視点から書かれた本は、いままでありませんでしたし、おそらくこれからもないでしょう。「米国の意向」について論じることは、日本の言論界ではタブーだからです。」(本書:「はじめに」より)
<戦後の日本外交は、米国に対する「追随」路線と、「自主」路線の戦いだった>
対米追随か、自主路線か、戦後長く続いた自民党政権についても、自主路線を選択、またはそれに傾いた首相は、米国によって排斥され、退場させられてきた。重光葵、芦田均(社会党)、鳩山一郎、石橋湛山、田中角栄、細川護熙(非自民)、鳩山由紀夫(民主)が挙げられている。竹下登、福田康夫も排斥されたグループに入ると著者は語る。そして、こうした自主路線派の排斥に協力した日本人の筆頭が吉田茂その人だというわけである。
著者は、長い外務省経験の一つとして、イラン油田の開発問題を取り上げている。1999年から2002年までイラン大使を務めた著者は、当時のハタミ大統領の訪日に尽力した。アザデガン油田の開発も絡めた外交戦略だった。しかし、「日本がイランと関係改善を行うのはけしからん」とアメリカから圧力がかかり、高村外務大臣は内閣改造で姿を消し、油田開発も断念させられ、最後は中国に開発権を握られる結果となった。日本の自主外交をアメリカが断念させた例として著者は明らかにしている。
本書は、1945年9月2日のミズーリ号での降伏文書調印、占領期を通じてのアメリカ支配、講和条約の締結、日米安保と地位協定、安保闘争と岸退陣、湾岸戦争と日本、9.11後のイラク・アフガニスタン紛争と日本など、まさに戦後史を紐解きながら、その中で起こった日本政界の「対米従属派」と「自主路線派」の戦いの歴史を、外交問題中心に語られている。
<対米従属路線を、墨守してきた自民党>
8月15日が「終戦」記念日とされている。しかし、国際的には、連合国と無条件降伏を定めた降伏文書に署名した1945年9月2日こそが、「敗戦記念日」に他なりません。まるで天皇が玉音放送で、戦争を止めたように描く、これが戦後の出発点であった、とすることこそ、日本の誤りであると著者は言います。
まさに無条件に連合国司令長官マッカーサーの指示に従う、これが吉田をはじめ戦後初期の政治家の「仕事」でした。その中でも、重光葵は一方的な占領政策に抵抗し、石橋湛山は、占領軍の費用負担の削減を要求した「自主派」であり、早々と圧力を受けて退陣を余儀なくされます。
その後、「日本国民の生活水準は、旧植民地国民より下であってはならない理由はない」と生産設備の破壊などの占領政策を行ってきたGHQも、朝鮮戦争、米ソ対立を受けて、「共産主義への防波堤」と日本の位置づけを変え、日本の産業の発展を認めることになります。
<60年安保闘争は、途上国型政権転覆策であったのか>
著者は、1960年安保改定を迎える中、岸首相の退陣をアメリカが画策したとの立場をとり、その根拠を示しています。岸は国会で、「日米地位協定は全面的に改定すべき時に来ている」と答弁し、アメリカの怒りを買ったと著者は語ります。
日本国内のどこでもアメリカの意のままに基地として使用できる、費用は日本が負担するという日米地位協定こそが、アメリカにとっての日米安保条約体制の根幹であり、地位協定の改定を主張した岸について、アメリカの軍部とCIAこそが退陣を画策したと言います。親米経済グループの経済同友会系から、全学連の闘争資金も出ていたのではないか、との指摘です。政変のために、デモや国内の紛争を焚きつけるというのが、アメリカの常套手段であるとも指摘されています。少々抵抗のある論説ですが、岸が「地位協定の改定」や、中国との関係修復に動いていたとの指摘は、新たな検討テーマであるとも考えられます。
<日米対立の事態を経て、日米共同体へ>
1970年代、80年代は、日本の経済成長に対して、アメリカに強い危機感が生まれた時期でした。その中でも田中角栄退陣の引き金であったロッキード事件は、アメリカに相談も無く、日中国交回復を行ったことへの報復ではないかと指摘しています。
また、1970年代には、外務省内部で、米軍基地の逐次整理・縮小のための政策が検討されていたり、政府内部にも外交的な自主派が存在していた。しかし、その後の湾岸戦争やイラン・イラク戦争などを経て、こうした勢力は力を弱め、日米共同体という、対米従属的な親米派が強くなっていると著者は語ります。
<戦後政治を俯瞰する内容>
著者孫崎氏は、「日米同盟の正体」他多数の著書があるが、一貫しているのは、外交における自主的立場を擁護することであり、アメリカに過度に頼らず、しっかりとした外交政策を独自に持つことを主張されている。鳩山由紀夫元首相が、政権交代を受けて、「アジア共同体構想」を打ち出したが、これもアメリカの抵抗にあったと言われている。
今、尖閣だ竹島だ、領土を守れ、と与野党が競っている。しかし、日米地位協定を墨守し、事実上のアメリカ「占領状態」にある日本の現状はどうなのか。アジアに目を向けた独自外交ができない日本にしてきたのは、吉田に始まる自民党内従属派の歴代首相たちではなかったか。本書は、戦後政治を俯瞰し、今問われている政治・外交の課題を我々に突きつけている。(佐野秀夫)
【出典】 アサート No.419 2012年10月27日
