【投稿】「横田先生の遺されたもの」 大曽良 宏
ついに横田先生も亡くなられた。やはり生きるものは永遠ではないことをあらためて知るべきだ。森先生は授業で「君は死んだら灰と思うか」と問いかけられていた。頑張ってみても仕方がないと思うか、と。そうでもない、とたいていの学生は答える。それでは生きがいとはどういうものか、何か残すほどのものを考えたことはあるか、と。
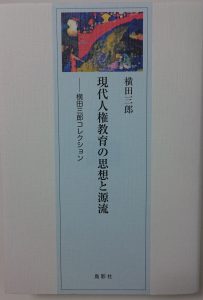
横田三郎 著
現代人権教育の思想と源流
—横田三郎コレクション—
2016年8月31日発行
鳥影社 2800円+税
ISBN978-4-86265-564-6
横田先生は終戦後入学された京都大学で鈴木祥蔵先生が主催されていた勉強会で『共産党宣言』を学び「目から鱗」でマルクス主義に傾倒された。1950年代に入ってすぐに大阪市立大学に勤めるようになると、そこでドブロリューボフの『オブローモフ主義とは何か』に出会い、大きな衝撃を受けられた。同時に同じ市大文学部におられた森先生と意気投合し唯物論哲学を学び、ロシア文学なども大いに語り合われたという。お二人の住まいは大学のあった大阪市内杉本町の駅の近くで、互いによく行き来して、将棋をさしたりしながら雑談に花を咲かせておられたようだ。横田先生のお宅には直木孝次郎先生も手みやげに寿司などを持って遊びにこられ、楽しいひとときを過ごされたこともよくあったと奥様からお聞きしている。このころはまだ時はゆっくりと過ぎていた。
1960年前後から世の中は騒然とし始め、大阪の部落解放運動も起こりはじめ、大学でも差別事件が告発されるようになってきた。60年代後半には大阪市内で誰もが知ってはいるが、どうしようもない問題として見て見ぬふりをされていた「差別越境」の問題に小学校の子どもたちも立ち上がった。そして越境していた子どもたちが地元の学校に戻ってくるにつれ、同和教育のあり方が真剣に問われることとなり、ついに「矢田教育差別事件」がおこった。この中で部落解放運動がおこなう糾弾とは何か、同和教育と先生の労働条件の関係、解放教育が任務とする「解放の学力」と進学できる学力との関係、非行や荒れる子どもたちをどう受けとめるかなど、問題や論点は多くの面に広がった。
横田先生はこの60年代をふり返って、「当時でもオレは十分に差別主義者だったよ」とおっしゃっていた。当時はまだ在日朝鮮人問題、障害者問題、女性問題、原爆被爆者問題、まして性同一性障害の問題などは、社会的にはほとんど受けとめられていなかった。部落解放運動や同和教育にかかわる人たちが先頭切って社会に問いかけ、孤軍奮闘している時代だった。
1960年代終わりから70年代にかけてのころ、大阪の人権運動は激動期を経て大きな発展をみた。横田先生は大学紛争や大学内部の差別事件、それに矢田教育差別事件などの渦中の人となって、相当深く考え、考え直して、真に民主主義的な考え方を体得されていったようだ。
誰が言ったのだったか、「横田さんは相当晩稲(おくて)だったのですなぁ」とは尊敬によるものか、真面目すぎるほどの繊細さを軽くからかったのかは知れないが、その両方に値する頑固な真面目さによって、終戦から長い時間をかけて幼いころからの軍国少年のくびきから自らを解放したのである。
横田先生の言葉には長い思索と苦しい自問とによって得た強い信念と迫力がこもっている。
このたび刊行された書籍には軍国主義を拒否し、民主主義に徹した一人の人間が求めた未来が描かれている。今日の教育問題に真摯に取り組もうとする人は、先ずこの本から始め、そしてこの本を乗り越えることが求められる。
【出典】 アサート No.465 2016年8月27日
