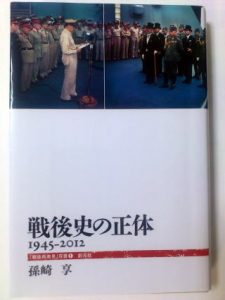【投稿】民主壊滅選挙と危険な安倍政権の再登場
<<「戦後最低の投票率」>>
民主党・野田政権の「自爆解散」は文字通りの、民主党の壊滅的とも言える敗北を自ら招き寄せ、自民党の圧勝に最大限の貢献をすることとなってしまった。自民党は絶対安定過半数とされる269をも突破し、294、公明党の31を合わせ、自公連立・計325で衆議院議席の総数の3分の2超えを達成させてしまった。選挙結果は、自民党294、公明党31、民主党57、維新の会54、みんなの党18、未来の党9、共産党8、社民党2、国民新党1、新党大地1、無所属5となった。この選挙結果によって、たとえ、民主や野党との合意がなく、法案が参院で否決されても衆院で再議決して可決することが可能となる事態を提供してしまったのである。もはや民主党は、たとえ自公連合に擦り寄ったとしても、その存在価値は極めて薄っぺらな軽いものと成り果ててしまった。
このような結果をもたらした今回の解散・総選挙が明らかにしたことを、取り急ぎここで改めて再確認しておくことは、今後の事態の展開を注視し、その問題点や矛盾点を明らかにし、本来あるべき活路を見い出す上で必要不可欠なことと言えよう。
第1は、今回の衆院選(小選挙区)の投票率が59.32%で、戦後最低だった1996年の59.65%もを下回る「戦後最低の投票率」を記録したことである。
政権交代が問われた、前回09年は69.28%で、小選挙区比例代表並立制が導入された96年以降では最高を記録していたものが、今回は10ポイント近く下落して、03年以来の60%割れとなったのである。維新の会が急伸した大阪でさえ、府内小選挙区の投票率は58.37%(前回66.79%)であった。当日有権者数は1億395万9866人で、このうち6166万9473人の投票であった。40%以上の棄権である。
有権者にとっては、民主党政権に対する怒りと絶望、政党への不信、政治総体へのあきらめがこのような低投票率をもたらし、政権交代の意義を継承できるような「入れる政党がない」、「入れる候補がいない」選挙区の続出をもたらし、投票所に足を運ぶ意欲をさえなくさせてしまっていたのである。そのような人々の多くが棄権に回った結果、選挙戦は総体として全く盛り上がりに欠け、自民党はただただ「敵失」によってだけ浮上、労せずして大量議席を獲得したのある。自民圧勝は野田首相の自爆解散によってプレゼントされたようなものである。個人の自爆は勝手であるが、政権交代の意義を全く台無しにしてしまった歴史的責任、その責任は計り知れないといえよう。
今回の衆院選で小選挙区に出馬した自民党候補は、300選挙区の有効投票総数のうち43%の票を得たのに対し、民主党は22.8%であったが、前回09年衆院選では得票率47.4%で半減以上の激減であったことからすれば、自民党はまさに低投票率と盛り上がらない選挙戦、民主党分裂や未来の党、日本維新の会など第三極の候補者乱立で票が分散し、結果として自民党が消去法的選択で「漁夫の利」を得た、その原因を作った民主党の自爆によって浮上したに過ぎないともいえよう。
いずれにしてもその結果、自民・公明両党は「合わせても4割に満たない支持(比例区で26.38+11.29=37.68%。有権者総数の22.33%)しか獲得していないにもかかわらず、衆議院議席の3分の2を上回る67.71%の議席を獲得したのである。
<<政策的対決における決定的な敗北>>
第2は、政策的対決における決定的な敗北である。
民主党にこうした凋落をもたらした決定的な敗因は、三年前の歴史的な政権交代の意義を自ら掘り崩し、嘘と詭弁で重要な政策をことごとく裏切ってきたことにあったことは論を待たないといえよう。問題は、有権者のこのような凄まじい怒りを肌で感じ取ることができず、公約にもない消費税増税路線やTPP参加路線を平然と押しすすめ、民主党執行部主流が、財務省の緊縮財政路線、社会保障・教育・セーフティネット切り捨て路線の忠実なしもべとなってしまったことであり、本質的には前自公政権が押しすすめてきた、政権交代選挙で否定したはずの新自由主義路線に逆戻りしたことである。
これに対して自民党、とりわけ安倍新総裁の路線は、政治・軍事における右傾化・緊張激化路線を掲げつつも、それを選挙の争点とすることを極力避け、もっぱらデフレ脱却路線としてのインフレターゲットの設定と、建設国債の大量発行、景気拡大路線、公共事業拡大路線に舵を切り、低迷する経済、不景気打破の決定打としてこれらをぶち上げ、呻吟する有権者の票をかっさらったことが、民主党との政策的対決において自民党に優位を確保させてしまったといえよう。
本来は、政権交代後の政権こそが、財政緊縮路線の呪縛を断ち切って、新自由主義路線と決別して、東日本大震災からの復旧・復興、原発事故を封じ込める脱原発路線、新たなエネルギー戦略への転換、社会資本インフラの再生、医療・介護・教育や社会的セーフティネットの再生と投資、雇用の拡大、といった、自公路線とは本質的に異なった新たなニュー・ディール政策を大胆に提起し、財政をそれらに総動員するデフレ脱却路線をこそ打ち出すべきであった。そしてそうした政策こそが、財政赤字を克服する正道であることを明確にすべきであったが、財務省に絡めとられた松下政経塾出身の未熟な執行部主流派には全く望むべくもなかった。
問題はこうした政策的対決において民主党内反主流派の多くの人々が、それなりに多く存在しながらも、あまりにも優柔不断、遅すぎ、すべてが後手後手、対抗勢力がばらばら、対決軸も明確に打ち出せないままに、時間切れの選挙戦に臨まざるを得ず、野党勢力が統一した協力体制や統一戦線を打ち出すことができずに、広範に存在している脱原発・憲法改悪反対・消費税増税反対・オスプレイ配備反対・TPP反対の圧倒的多数の声を集約し、まとめられないまま後退してしまったことである。
<<危なっかしい政治情勢の到来>>
第3は、今回の選挙によってタカ派が臆面もなく前面に登場し、ハト派勢力がさらに後退するという、危なっかしい政治情勢の到来、日本政治の右傾化・超保守化をもたらしかねい情勢を作り出してしまったことである。
安倍氏は首相就任わずか1年、「総理大臣の職責にしがみつくことはしない」と言って、「所信表明直後の辞任」で内閣を投げ出した人物である。この時点で政治生命が終わったかに見えたが、それから5年で運良く復活したわけである。本来なら復活できなかったはずであるが、尖閣列島をめぐる石原前都知事の挑発行為と日中緊張激化、領土ナショナリズムの時流に便乗できたわけである。社会の保守化と右傾化、それを法的に可能にする憲法改正が自らのライフワークと公言する人物の再登場である。5年前、安倍氏は、「美しい国」、「戦後レジームからの脱却」を旗印に、「5年以内の憲法改正」、集団的自衛権行使の合憲解釈、「教育改革」と教育基本法改正を掲げ、憲法改正国民投票法の制定と教育基本法の改悪を強行した。そして従軍慰安婦問題での国家・軍関与の否定とその関与を認めた河野官房長官談話の否定を公言し、韓国をはじめとするアジア諸国との対立を厭わない、未だに蒸し返し固執するウルトラ右翼につながる人物である。
そして今回、「醜い憲法」と言い募る”暴走老人”・石原慎太郎氏も憲法改正が同じライフワークで、選挙運動のさなかに「9条のせいで日本は強い姿勢で北朝鮮に臨むことができなかった。9条が自分たちの同胞を見殺しにした」として、日本維新の会は自民党、安倍政権と組んで憲法改正を行うことを宣言している。そしてすでに「維新」の橋下代表代行は首相指名選挙で安倍総裁を支持すると発言している。
ますは9条改憲への足がかりとして、集団的自衛権行使を可能にする動きは、民主党改憲派をも含めて、今後一気に勢いを増す可能性が大であると言えよう。自衛隊の「国防軍」への再編強化、日本版海兵隊の創設、先島諸島への軍事力配備、防空・ミサイル防御体制の強化等々が矢継ぎ早に打ち出される可能性が大である。
こうした中で自民・公明連立は、改憲に慎重な公明に代わって、「維新」が連立に割って入って3分の2を確保し、安倍氏本人が最も望んでいる「改憲(壊憲)連立政権」となる現実的可能性さえ存在しているといえよう。さらには自公連立+維新+民主の危険な大連立、翼賛政権の可能性さえ否定できない情勢の到来である。
しかし問題はこうしたタカ派路線の台頭と現実化は、日本国内のみならず、日本の世界からの、とりわけアジアからの孤立化を招き、安倍新政権が掲げる「デフレからの脱却」をますます困難なものにさせるものであり、一気呵成には進められない、早晩行き詰まらざるを得ない致命的弱点を抱えていることである。国内においてさえ、あの軍事オタクと言われる自民党の石破幹事長が12/16日夜の記者会見で、米軍普天間飛行場の移設先について「選挙中も言ったが、最終的に県外移設というゴールにおいて、党本部と沖縄県連に齟齬はない」「普天間が今のまま(固定化)ということをいかに回避するかが最大のポイントだが、辺野古移設はベストでなくワーストだ」と語らざるを得ない事態である。ましてや台中、対韓、対アジア外交においての緊張激化路線、軍事力増強路線は、日本の政治的孤立化にとどまらず、経済的な孤立化をさえ招きかねない。現実の日本を取り巻く環境は、野田政権よりずっと柔軟な対外緊張緩和路線を取らなければ、日本経済への打撃は予想以上に大きく、現実の生きた経済の活性化は望めないのである。
さらに安倍新政権が、危険極まりない原発再稼働路線に踏み出せば、世論からの反撃と孤立化、いつ襲い掛かるとも知れない自然からの巨大なしっぺ返しを招きかねない。威勢のいい圧勝の足元は、実は全てがぐらついていることを再認識せざるをえない客観的現実が横たわっているのである。
脱原発・反増税・改憲阻止・緊張緩和と対外友好路線の確立を求める多様で広範な包囲網と統一戦線の形成が要請されている。
(生駒 敬)
【出典】 アサート No.421 2012年12月22日