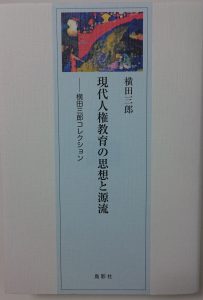【投稿】過去の反省を無視し「軍事研究」に踏み出そうとする日本学術会議
福井 杉本達也
1 「軍事研究」に前のめりの日本学術会議
科学者の代表機関とされる日本学術会議は第二次世界大戦で科学者が戦争に協力した反省から、1949年「わが国の科学者がとりきたった態度について反省し、今後は科学が文化国家ないしは平和国家の基礎である」という発足声明を発し出発した。1950年の第6回総会では物理学者の坂田昌一(2008年ノーベル物理学賞受賞者の小林誠、益川敏英の恩師)らが主導して「戦争を目的とする科学の研究には絶対従わない」と決意表明をした。ところが、1959年から1967年にかけ、アメリカ軍極東研究開発局から全国の大学、民間研究機関が研究資金をうけていたことが明らかとなった。日本物理学会では米軍から半導体国際会議の資金援助を受けていた。そこで改めて1967年に「戦争を目的とした科学の研究を行わない」という声明を出した。ところが、今回、軍事目的の研究を否定する原則の見直しに向け検討を始めた。政府が「デュアルユース(軍民両用)」技術の研究を掲げる中、「時代に合わない」として、5月20日の幹事会では、「安全保障と学術に関する検討委員会」を設置し、声明が見直される可能性が出てきた。2015年度から防衛省が防衛装備品に応用できる最先端研究に資金を配分する「安全保障技術研究推進制度」を始め、大学などの研究9件が対象に選ばれた。2016年度から始まった国の「第5期科学技術基本計画」でも関連技術の研究開発推進が盛り込まれた。今回の制度を受け、声明の見直しも含めて、議論を続けている(毎日:2016.5.21)。大西隆会長(豊橋技術科学大学学長)は11月28日の日経紙上においては、「自衛装備が直ちに戦争につながるとの主張は強弁にすぎる」とし、「自衛目的に限定して、大学などの研究者が将来の装備品開発に役だつかもしれない基礎的な研究をすることを可能とする」(大西隆:日経:2016.11.28)と述べるなど、軍事研究に前のめりの発言を繰り返している。
2 札束で研究者の顔を引っ叩く防衛省
防衛省は5月31日、過去最大の総額5兆1685億円に上る2017年度予算の概算要求を発表した。16年度当初予算比2.3%増。このうち、企業や大学に対し、軍事に応用可能な基礎研究費を助成する「安全保障技術研究推進制度」予算として、16年度の6億円から18倍増となる110億円を要求した。安全保障技術研究推進制度は、防衛技術の基盤強化などを目的に2015年度からスタート。防衛装備庁が提示した研究分野に、大学や企業の研究者が研究計画を提案。採択された研究者は、3年間で最大9千万円の研究費を得て、同庁の助言を受けながら研究する。2015年度事業として助成を受けた主な研究は、東京工業大学の「運搬可能な超小型バイオマスガス化発電システム」3900万円、理化学研究所の「光を完全に吸収する特殊素材の開発」3898万円、豊橋技術科学大学の「極細繊維による有害ガス吸着シートの開発」390万円などがある。
これまでも防衛予算のうち科学技術関連予算は1千億~1500億円、毎年計上されてきた。防衛装備庁は来年度から、導入済みの委託研究制度に加えて、1件あたり5年間で最大10億~20億円の大型研究プロジェクトを新たにスタートさせる。防衛産業の市場規模は約1.8兆円。国内の靴・履物小売市場(約1.4兆円)に等しく、勢いはない。国内防衛産業は、防衛省の発注でほとんどが支えられているが、ここ数年、急速に輸入比率が高まっており開発への焦りが背景となっている。
3 仁科芳雄と戦前の原爆研究
兵器は技術者や軍人によって経験主義的に試行錯誤をへて作られたが、原爆はその原理も可能性も「科学が主導した技術」(武谷三男)として100%物理学者の頭脳の中から生みだされた。第二次世界大戦中継続して原爆の製造を追求したのは米国と日本だけである(ドイツは1942年頃には製造を諦めている)。米国のマンハッタン計画では12万人もの研究者や技術者が動員され、230億ドルの資金(現在価値)が投じられたといわれるが、日本では1941年に陸軍が理化学研究所に原子爆弾の開発を委託した。仁科行雄が研究を主導し「二号研究」と呼ばれ、武谷や朝永振一郎らの物理学者が従事した。今日の価値で10億円という金額が投じられた。一方、海軍は京大理学部教授の荒勝文策に委託し「F号研究」と呼ばれた。湯川秀樹らが従事している。
4 生物化学兵器の研究を行った731部隊の医師・研究者
1936年、日本は中国・満州ハルピンの郊外平房の広大な敷地に研究施設を作り細菌兵器の開発を目指した。その中心が陸軍軍医少佐の石井四郎であった。中国人・朝鮮人・ロシア人・モンゴル人などをマルタと称して生体実験・生体解剖などをし、試行錯誤を重ね、より強力な細菌兵器の開発を目指した。戦後、731部隊の戦犯追及は停止され、詳細なデータはアメリカが独占することになり、東京裁判では731部隊のことは裁かれなかった。マッカーサーは自国の遅れていた細菌兵器の開発に日本軍のデータが役立つとして、細菌戦や細菌兵器のデータが欲しかったのである。
731部隊をはじめとする生物化学兵器研究の幹部は、エリートが多く、そのほとんどは戦後になって、東京大学や京都大学を初めとする医学部の教授、国立予防衛生研究所所長など、日本の医学界、医薬品業界、厚生行政の重鎮となった。北岡正見731部隊ウイルスリケッチア部長は国立予防衛生研究所の幹部となった。福見秀雄(細菌第2部長)は戦後も国立第1病院等で乳児に致死性大腸菌の感染人体実験を行ない、国立予防衛生研究所所長をへて55年長崎大学長となっている。
5 宇宙開発と軍事研究に「垣根」はない(糸川英夫から始まる日本のロケット開発)
12月9日、宇宙航空研究開発機構(JAXA)と三菱重工は国際宇宙ステーションへの無人補給機「こうのとり」6号をH-2Bロケットで軌道に載せることに成功した。日本のロケット技術は最近安定してきているが、日本はHⅡA、HⅡBというロケットを開発し、15t~20tの打ち上げ能力がある。核兵器を搭載できる大陸間弾道ミサイルとして遜色のないものである。打ち上げ成功を手放しで喜ぶべきものではない。2010年、小惑星の探査を目的として打ち上げられた「はやぶさ」が地球の大気圏に再突入し、小惑星「イトカワ」の微粒子を持ち帰ったことが大きな話題となったが、「イトカワ」とは戦時中、戦闘機「隼」を設計し、戦後はいち早くペンシルロケットなどミサイルの開発に着手した軍事技術研究の第一人者である糸川英夫から命名されたものであり、最初から軍事技術と宇宙開発は切っても切れない関係である。宇宙の軍事利用に合法的道を開く宇宙基本法が08年に施行され、JAXAと防衛省の技術交流が拡大した。小惑星探査機「はやぶさ」の耐熱シールドは、弾道ミサイル技術に通じる。核弾頭が大気圏再突入の際、大気圏外で爆発されては効果がない―どころか自国に被害が生じる。宇宙基本法の施行以来、学術研究の場といえども研究情報が機密保護の管理下に置かれつつある。
6 作ったもの(兵器)は必ず使用される―「デュアルユース」などというものはない
防衛省は安全保障技術研究推進制度の募集要領で「広く外部の研究者の方からの技術提案を募り、優れた提案に対して研究を委託するものです。得られた成果については、防衛省が行う研究開発フェーズで活用することに加え、デュアルユースとして、委託先を通じて民生分野で活用されることを期待しています」と書いている。しかし、兵器の最終目的は人間を「より大量に」・「より素早く」・「より残虐に」殺すことである。作った兵器は必ず試されなければその効果は分からない。原爆はアインシュタイン書簡により、当初、ナチス・ドイツの原爆研究に対抗する目的で科学者の動員が図られたが、1945年5月のドイツ降伏前の44年9月には米大統領ルーズベルトと英首相チャーチルは投下目標を日本に絞ることで合意していた。日本への原爆投下は米国を第二次世界大戦後の世界において有利な立場を置き、主導権を握るために行われたのである。そして、原爆の破壊力を試すのに、市民殺傷効果を見るのに最適な規模の人口密集地で空襲を受けていない都市である広島・長崎が選らばれた。しかも、長崎に投下されたファットマン(Fat Man)はプルトニウム型原爆であり、広島に投下されたウラン濃縮型とは異なった効果を試すために戦略的には無用な2発目の原爆が落とされたのである。古田貴之・千葉工業大未来ロボット技術研究センター所長は「軍事利用を含め、自らの研究成果が世の中でどう使われるか、用途を研究者も考える責任があるということは特に強調したい。真理の追究が職務だと言い逃れる人もいるが、それでは今の時代は済まされない。私たちは不可能を可能にし、社会を良くしたいと願ってロボットを研究している。その成果が悪用されないよう、少なくとも用途を予測する努力は必要だ」(古田:毎日2016.7.27)と述べる。 兵器には「デュアルユース」などというものはない。必ず人間を殺すために使用される。予算で締め付けを食う研究者はいま大きな転換点を迎えている。学術会議は「カネ」のために最後の一線を越える気である。
【出典】 アサート No.469 2016年12月24日