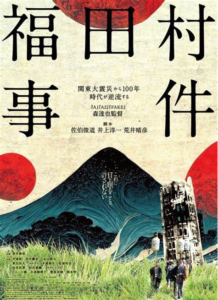<<紅海封鎖が西側経済に「激震」を与える可能性>>
世界経済全体、とりわけ西側・米欧経済に「激震」を与える可能性が取りざたされ、現実化している。その象徴的な事態が、エジプトのスエズ運河につながる紅海海峡を通るイスラエル向けの船舶に対する、イエメンのアンサール・アッラー抵抗運動Ansarallah(フーシ派)による封鎖(12/9 発表)である。イエメン軍の報道官、ヤヒヤ・サレエ氏は、イスラエルがガザ地区での虐殺・ジェノサイド戦争を終了し、包囲されたパレスチナ領土の封鎖を解除するまで、200万人以上の飢えている人々への人道援助が許可されるまで封鎖を続けると発表している。これは、反イスラエル・反米欧・反西側「抵抗枢軸」のアラブ諸国の中核となっている、ヒズボラ、ハマス、アンサール・アッラーによる協調した反撃行動の一環でもある。この抵抗枢軸グループは、この中東地域全体で連携し、統一戦線としてイスラエルと対峙し、ガザとヨルダン川西岸、レバノン、シリア、イラクで協調した行動をとっており、いずれも、過去20年間で軍事能力を大幅に向上させている。そして今回、実際に、アンサール・アッラーは石油を積んでイスラエルのアシュドド港に向かうノルウェーの船にミサイルを発射し、12/14には、イスラエル行きのマースク・ジブラルタル船をドローン攻撃したと発表している。紅海封鎖の標的となっているのは、イスラエルの大量虐殺という国際法違反を支援し、イスラエルにエネルギーや物資を届ける、日本を含む西側諸国の船舶である。すでにミサイルやドローンによる封鎖攻撃は実行されているが、イスラエルの港に向かわない船は攻撃されないと繰り返しており、ロシアのタンカーや、中国、イラン、グローバル・サウスの船舶は、紅海を平穏に航行し続けている。
 この交通量の多い紅海海峡は、最狭地点=バブ・アル・マンデブ海峡は33kmに過ぎないが、世界貿易の実に10% から 12% を担っている。パナマ運河の5%よりも倍以上大きいのである。紅海を通過する石油輸送量は、日量 880 万バレル、貨物輸送量が 1 日あたり約 3 億 8,000 万トンに達している。
この交通量の多い紅海海峡は、最狭地点=バブ・アル・マンデブ海峡は33kmに過ぎないが、世界貿易の実に10% から 12% を担っている。パナマ運河の5%よりも倍以上大きいのである。紅海を通過する石油輸送量は、日量 880 万バレル、貨物輸送量が 1 日あたり約 3 億 8,000 万トンに達している。
すでに、エネルギー大手BP社は声明で、「紅海における海運の治安状況の悪化を考慮し、紅海を通るすべての輸送を一時的に停止することを決定した」と発表(12/18)、続いて世界の大手海運会社5社が航行を停止(マースク、ハパックロイド、イタリア・スイスおよびフランスの企業であるCMA CGM、地中海海運会社)、これに台湾のコンテナ輸送会社エバーグリーンも追随。現実に、紅海通過を目指していた46隻のコンテナ船が現在、南アフリカ・喜望峰回りに迂回を余儀なくされている。
当然、輸送コストが大幅に高騰し、航海距離が 40% 増加し、航海期間も2週間の追加が必要となり、輸送保険料も上昇。BP発表後の12/20のブレント原油価格は、2.7%上昇し、1バレル=78.64ドルとなり、米国産原油も2.8%上昇し、1バレル=73.44ドルに上昇。天然ガス価格も上昇、ヨーロッパの天然ガス価格は 7.7% 上昇している。商品価格とインフレの上昇がさらに想定されるのは当然と言えよう。それは必然的に、サプライチェーン不足と消費者物価上昇により、苦境に立たされている米欧・西側経済に危機の深化と悪影響を与えることは言うまでもない。
<<動揺し、うろたえる米バイデン政権>>
こうした予期せぬ事態の進行に動揺し、うろたえる米バイデン政権は、12/20、「イエメンのフーシ派による無謀な攻撃」に怒りに駆られて、「すべての国の航行の自由を確保し、地域の安全と繁栄を強化することを目標に、紅海南部とアデン湾の安全保障上の課題に共同で対処する」ために、「繁栄の守護者作戦(Operation Prosperity Guardian)」なる軍事作戦を開始すると発表した。「イエメン発のフーシ派による最近の無謀な攻撃の激化は、自由な通商を脅かし、罪のない船員を危険にさらし、国際法に違反している。」などとぬけぬけと述べているが、アメリカが直接関与し、支援しているイスラエルの国際法無視の、「罪のない」パレスチナ人大量虐殺・ジェノサイドには一言も言及していない。
 この米国防総省・ペンタゴン主導の海軍機動部隊は、紅海全域を航行する商業船舶を保護することを名目に、イエメンの攻撃からイスラエル関連の商船を守ると主張している。オースティン米国防長官の発表によると、この作戦、有志連合には、英国、バーレーン、カナダ、フランス、イタリア、オランダ、ノルウェー、セーシェル、スペイン、そして米国が参加する、と言う。
この米国防総省・ペンタゴン主導の海軍機動部隊は、紅海全域を航行する商業船舶を保護することを名目に、イエメンの攻撃からイスラエル関連の商船を守ると主張している。オースティン米国防長官の発表によると、この作戦、有志連合には、英国、バーレーン、カナダ、フランス、イタリア、オランダ、ノルウェー、セーシェル、スペイン、そして米国が参加する、と言う。
 ところが、である。この地域のアラブ諸国のうち、名を連ねているのはバーレーンだけである。アメリカの同盟国であったはずの肝心のサウジアラビアが欠落している。スペイン、フランス、イタリアといった他の帝国主義国家でさえ、ペンタゴン主導の介入への参加を拒否している。スペインは関与を否定し、「紅海作戦には一方的に参加しない」と表明し、フランスはペンタゴン指揮系統の下で機能することは望んでいない、と言う。
ところが、である。この地域のアラブ諸国のうち、名を連ねているのはバーレーンだけである。アメリカの同盟国であったはずの肝心のサウジアラビアが欠落している。スペイン、フランス、イタリアといった他の帝国主義国家でさえ、ペンタゴン主導の介入への参加を拒否している。スペインは関与を否定し、「紅海作戦には一方的に参加しない」と表明し、フランスはペンタゴン指揮系統の下で機能することは望んでいない、と言う。
バイデン政権が最も期待をかけていたサウジアラビアは、もはやイエメンとの8年間続いたアメリカが支援した戦争を継続する意思が失せ、イエメン諸派との関係を改善する方向に傾き、親イスラエルの「プロスペリティ・ガーディアン作戦」への参加に関心がないことがすでに報じられている(12/25 ニューヨークタイムズ紙)。この米国主導の軍事作戦・有志連合は、発表されるやたちまち政治的困難と内部危機に直面しているのである。
<<バイデン:2期目獲得できなかった過去4人の支持率よりも低い>>
かくして、2023年・年末は、米国一極支配・ドル一極支配のリーダーシップが象徴的に崩れ去る歴史的「転換点」を全世界に明らかにしたのである。ウクライナ、BRICS、ガザ、いずれにおいても、米帝国一極支配構造は、後退と敗退を余儀なくされている。
ロシアをウクライナ危機に引きずり込み、ロシア・EUのノルド・ストリームパイプラインを破壊して、欧州のエネルギーコストを戦前の2.5倍とさせ、EU経済をガタガタにし、さらに全面的金融制裁でロシアを孤立させたはずが、ウクライナを疲弊と泥沼の戦争に追い込み、ブーメランで逆にドル一極支配体制自体が維持できない事態をもたらしてしまった。
対照的に、BRICS諸国は 11か国と拡大し、世界の GDP の 37% を占めているのに対して、西側 G7 諸国では 30% に落ち込んでいる。その中でも重要なのは、米国の忠実な同盟国であったサウジアラビアがBRICSに加盟し、ロシアと合わせて世界の石油の44%を生産、石油と密接に結びついていた国際基軸通貨としてのペトロダラー体制が有名無実化し、脱ドル化を加速させる事態をもたらしてしまったのである。
そして、イスラエルのパレスチナ・ガザ大虐殺攻撃へのバイデン政権の無条件加担・共謀は、決定的に米国一極支配の優位性、道義的信頼性を一挙に崩壊させ、「ノーモア・ジェノサイド」の声の前に世界的な孤立化を促進させてしまい、結果として、米帝国一極支配の慢心は、行き詰まり、孤立と動揺に揺れ動いているのである。
米帝国が過小評価していたイエメンの紅海封鎖攻撃にたいしても、それを防止しえない、阻止することも、未然に囲い込むこともできない、場合によってはイエメンのミサイル攻撃に対して米重量艦隊が意外に脆弱であることを
さらけ出してしまったのが現実である。
アメリカン・リサーチ・グループが12月17~20日に実施した最近の世論調査によると、バイデン大統領の支持率は37%で、57%が不支持であった。この支持率は、2期目を獲得できなかった過去4人の大統領の支持率よりも低いことが明らかにされている。ハリス大学とハーバード大学の最新世論調査によると、有権者の62%がバイデン氏が大統領の職務を遂行するのに適任であると疑っており、さらに48%が彼の大統領職は年々、月ごとに悪化していると考えている、と報道されている。NYTの世論調査によると、18歳から29歳までの有権者の75%近くがバイデン氏のガザへの対応を支持していない。
この2023年末の「画期的」な「転換点」は、もはや元に戻りえない、米帝国、ドル一極支配体制の全面的後退の到来を明らかにしていると言えよう。
(生駒 敬)